|
�P�@���N���i�A���a�\�h��ڎw������ۗ{�n�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�
�i�P�j����ۗ{�n�Ƃ�
�@�ۗ{�Ƃ́A��J���������߂̋x�{�Ƃ͈���āA�S�g�@�\�̉A���i���͂���A�܂����a�\�h�̂��߂ɁA���퐶�������痣�ꂽ�ꏊ�ɓ]�n�؍݂��A�����ʼn^���E�h�{�E�x�{�̌��N�Â���O�v�f�����H���邱�Ƃł���B���̏ꏊ���ۗ{�n�ł���i�Q�P�j�B
�@���{�͓�k�ɒ����A�R�A�C�A�X�тɌb�܂�Ă���B����͎��R�̖L���ȂƂ���ɗN�o���Ă���A����n�͎��R�̓������A��C���A�����������ɍs����ꏊ�ł���B����ۗ{�n�ł́A�����݂̂Ȃ炸�x�{�E�ۗ{�A�^���A�h�{�A���h�����܂߂������I���Â��s�Ȃ���B
���p�̗��j�͌Â��A���m�ł͌Ñ�M���V���ɁA�킪���ł͐_��ɋL�^������B�Â�����A���{�ł͉���Ö@�́u�����v�Ƃ��Đe���܂ꗘ�p����Ă����B�����l�X���]�ɂ𗘗p���ĐS�g���x�߁A���N�̑��i���͂���A�����ւ̋ΘJ�ӗ~��{���Ƃ��낪����n�ł������B
�i�Q�j���a�\���̕ω��Ƒ�
�@���a�͐l�ނ̒a���Ƌ��Ɏn�܂�A�a��̍����͌��n���ォ�瑱���l�ނ̊肢�ł������B����Ƌ��Ɏ��a�\�����ω����A�Ñォ��19���I�ɂ����đ������������a�́A�h�{����̉��P�A�R�������̏o���ɂ�蒘�������������B����A�A�����M�[�����A�X�g���X�ɂ�鎾������K���a�͑����̈�r�����ǂ��Ă���B�����K���a�Ƃ́u�H�K���A�^���K���A�x�{�A�i�����̐����K�������̔��W�E�i�W�ɊW����nj�Q�v�������A�������ǁA���A�a�A�얞�ǁA�咰���A�z��a�A�x���A�A���R�[�����̎����Ȃǂ��܂܂��B
�@���a�\�h��}�邤���ŁA�H�����A�^���A�x�{�A�i���A�����Ȃǂ̐����K���ւ̑d�v�ł��邪�A���̂��߂ɂ͎��a�𖢑R�ɗ\�h���A���N�I�Ȑ����𑗂邱�Ƃ�ړI�Ƃ���ꎟ�\�h�A���a�̑��������⑁�����Â�ړI�Ƃ���\�h�A����ɂ͕a�C�ɂȂ��Ă��Q������ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���@�\��Ĕ��h�~�ɂƂ߂�O���\�h�ȂǁA�����I�Ȍ��N���i�������K�v�ł���B����12�N�x����́A����22�N�x��ڕW�Ƃ������N�Â���^���Ƃ��āA���N���{21�i21���I�ɂ����鍑�����N�Â���^���j���J�n����A�����̌��N�ւ̊S�͍��܂���݂��Ă���B
�@�ŋ߁A���E�҂̑��������ɂȂ��Ă���B2002�N��1�N�ԂɎ��E�����l�͂R���Q�P�S�R�l�ŁA�O�N�x���P�P�O�P�l�����A�T�N�A���łR���l�����B���̌����Ƃ��Č��N���i���a�Ȃǁj�A�o�ρA�������A�ƒ��肪�w�E����Ă���B�����^���w���X�͍ŋ߂ɂ�����d�v�ȊS���ł���B�����w�̐i���͒������A�Q�O���I�㔼�Ɏ���A���q���x�����琶���̖{�������炩�ƂȂ��Ă����B��`�q�f�f�A��`�q���Â������̂��̂ƂȂ����B�l�H����A����ڐA�A�Đ���ÁA���{�b�g��p�A�Đ���Â��s�Ȃ��Ă���B�����w�͕a���̉𖾁E�����ɂ͋P���������ʂ����������A�K�����������̎������P���A����������^������̂ł͂Ȃ������B
�@�]�܂�����ÂƂ͒P�Ȃ鉄���ł͂Ȃ��A�����E�����̎��iQOL, quality of life�j�����P���邱�Ƃł���B���o�Ǐ�݂̂Ȃ炸�K�����A��������^������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B����ۗ{�n��Â͐l�Ԃ�S�̓I�ɂƂ炦�A�{�������Ă��鎩�R�����͂����߁A�ߑ��Âƕ⊮�������AQOL�̍�����Âɖ𗧂��Ƃ����҂����B
�i�R�j��������ۗ{�n�̑I��
�@����@�͏��a�Q�R�N�u�����ی삵�A���̗��p�̓K����}��A�����̕����̑��i�Ɋ�^���邱�Ɓv��ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ�i�Q�Q�j�B���a�Q�X�N�ȗ��A�\1�Ɏ����悤�ȗv���������̂��A��������ۗ{�n�Ƃ��Ďw�肳��Ă���i�Q�R�j�i�\�Q�j�B�����P�R�N�i2001�N�j���݁A�W�X�P���ɒB����B����ɁA���̍����ۗ{����n�̒�����u�����ی�����n�v�Ɓu�ӂꂠ���E�₷�炬����n�v���I�яo����Ă���B�u�����ی�����n�v�̑I��ɂ́A����a�@�⌒�N�Z���^�[�Ȃnj����I�Ȏ{�݂��[�����Ă��邱�Ƃ���ӊ����D��Ă��邱�ƂȂǂ������ƂȂ�B
�\�\�P�@�����ۗ{����n�̑I��
����̌��\�A�N�o�ʋy�щ��x�Ɋւ������
�P�D ����������ł��邱��
�Q�D �N�o�ʂ��L�x�ł��邱��
�R�D ���p��K���ȉ��x��L���邱��
����n�̊��Ɋւ������
�P�D ���q���I�������ǍD�ł��邱��
�Q�D ���߈�т̌i�ς����ǂł��邱��
�R�D ����C��w�I�ɋx�{�n�Ƃ��ēK���Ă��邱��
�S�D �K�Ȉ�Î{�y�ыx�{�{�݂�L���邩���͏����{�݂����邱��
�T�D ��ʂ̔�r�I�֗��ł��邩���͕֗��ɂȂ�\���̂��邱��
�U�D �ЊQ�ɑ����S�ł��邱�� ����ږ�オ�C������Ă��邱��
|
�\�\�Q�@�����ۗ{����n�ۉ���n
�k�C���G���A
�L�x����A����������A�\���쉷��A��ʉ���A�R�ʋ�����A�\���x���A
���ʉ���*�A�Ȃ��ʂ܉���A�u����A�~�Z�R���A����E�z���܂艷��A
�k����A�J�����X����A�L�������A�b�R���A���Љ���
���k�G���A
����A�_��������A�c��������A�H�m�{����A���c�ꉷ��A
���������A�Ė�����A�{��E�^������*�A���q�E��n���A �I�܉���*�A
��R����A��_����*�A��������A�y���E�������A�x����A�V�b�q����
�֓��G���A
������A������������A�Еi���A�y�q�E�ޏ���A ���h�E��ÁE�@�t����A
�l������*�A����
�����G���A
��F�E�������A�Ȕ����E��V������*�A�Z��������A�։�����A���J����A
�B�쉷��A�c��E�B�|����A�����E�䍂����A�ێq����*�A����������*�A
��������A���x����A��������*�A���сE�ތÒJ����A�����E����ˉ��A
���≷�A���싽����*�A���R����
�ߋE�G���A
�v���̕l���A���k��������A�l�≷�A�\�Ð쉷��*�A���_���A
�F��{�{����*�A���m������
�����E�l���G���A
��䉷��A����E�g������A������A���É���*�A��������A��̓�����A
�O�r����A�U�R����*�A�O�u����*�A�������̎R����*�A���m�Y����
��B�G���A
�}��쉷��A�g�䉷��A�Ó��F�̐쉷��*�A���E���{����*�A �_��E���l����A
�S�ցE���H�E�ĐΉ���*�A���z�@����*�A��������A �쏬��������A�V�����c����A
���m�߉���*�A��������A���l�E�V��k�J����
�������ی�����n
|
�i�S�j�ۗ{�n�Ö@�̖ړI
�@�ۗ{�n�Ö@�̖ړI�Ƃ��ẮA�\�h�A���n�r���e�[�V�����A���������ɂ�����×{����������B
�@�\�h�ɂ́A�����K���a�ɂ����郊�X�N�t�@�N�^�[�̏����A�ϋɓI���N�Â���̂��߂̋���A�w���A�̌��Ȃǂ��܂܂��B
�@���n�r���e�[�V�����̓K���Ƃ��Ă͔]���Ǐ�Q�̌��ǁA�O�Ȏ�p��A��ʎ��̂�X�|�[�c�O���ɂ����ǂ�����B
�@�×{�́A��܂�K�v�ŏ����x�ɂւ炵�AQOL�̌����}��A���̖h��͂����P���邱�Ƃł���B
�Q�@����n�̂ق��n�`�A�C�ۂȂlj���n�Ƃ��������A�ǂ̂悤�Ȋւ�ŕۗ{���ʂ������炳���̂��B
�@����n�Ƃ����A�s��ɂ���w���X�Z���^�[���̎{�݂������āA�����͎R���A���邢�͊C�ɖʂ��Ă���B�R�ł���A�����ɂ͐X��т�����A�ŋ߁A���ڂ����X�ь��ʂ����҂����B������ʂ́A����݂̂̌��ʂłȂ�����n�̋C��⎩�R�����W���Ă���B����ɂ��̓y�n�ł̐l�Ɛl�̃R�~���j�P�[�V������l����W����B
�i�P�j�C��v�f�Ɛ��C��
�@�C����\������e�v�f�ƁA���̍�p�l����\�R�Ɏ����i�Q�S�j�B����n��ł̋C��̓����́A�C���⎼�x�Ȃǂ̌X�̗v�f�̓��F�����łȂ��A���v�f�̑�����p�Ō��܂�i�Q�T�j�B
�\�|�R�@�C��v�f�Ɛ��̂ւ̍�p
�P�D ���M�I�v�f�i�C���A�����C�A���ˁA�ԊO���A���̕ϓ��j
�@�@�@�̉��A�z�A�ċz�����@�\�ɏd�v�A�V��ӂւ̍�p
�Q�D ���x�i�����ё��Ύ��x�j
�@�@�@�P�Ɠ��l�̍�p
�R�D �@�B�I�E�͊w�I�v�f�i�C���A�����j
�@�@�@�Ƃ��ɍ�����ሳ���̏z��n�A�ċz��n�A������n�A
�@�@�@�����_�o�n�ւ̍�p�A���t�K�X�����ւ̉e��
�S�D ���w�I�v�f�i�y�f�A�I�]���A�Y�_�K�X�A�e���y���ށA
�@�@�@�V�R����с@�l�H�L�Q���������j
�@�@�@�ċz��n�A�z��n�A���t�����ւ̉e��
�T�D �����v�f�i�������A���O���j
�@�@�@���O���͇@�g���`���A�A�F�f�����A�B�r�^�~���c�����A�C�E�ۍ�p
�U�D �d�E���C���v�f�i��C�C�I���A�d���g�Ȃǁj
�@�@�@�����_�o�n�ւ̍�p�A�Z���g�j�������p�Ȃ�
�V�D �s�������I��p�i���j ���̃��Y����s���ɑ����p
|
�@�ۗ{�n�C��́A1�N��ʂ��Ă̐��̂ɑ���h���̒��x�ɂ���ĂR�ɕ�������B
�P�j�@�ی쐫�C��
�@�C����C���̕ω������₩�ŁA����̍������Ȃ��B���˂����₩�ŁA��C�͐���ł���B�A�����L�x�ŋC��̋}���ȕϓ���h���ł���B�S�̓I�ɕی�I�A���ÓI�ɍ�p����C��ŁA����҂ɂ��K���A�a��̌��N�A�S�g�ǁA�X�g���X�a�ȂǕ��L���K���ǂ�����B
�Q�j�@�h�����C��
�@�C���⎼�x�̓����ϓ���N�ԕϓ����傫���A�����ɂ��C���ቺ���������B���˂⎇�O���ʂ������A��_�f�ȂǂŁA����������̂Ɏh���I�ɍ�p����B�����̋C��h���ɑς�����̗͂�\���\�͂�����A�ϋɓI�ɐ��̋@�\�̃g���[�j���O�ɉ��p�ł���B
�R�j�@���א��C��
�@���������▶�Ƃ��������₽���������ԑ����C��B�������ꂽ��C����˕s���������ԑ����C��ŁA�ۗ{�ɂ͕s�K�ł���B
�i�Q�j�W������ɂ����C��̕��ށi�\�S�j
�P�j�@�C�ݐ��C��ƊC�ݗÖ@�iThalasotherapy�j
�@��ʂɓ����͗��n�͔M�����C���͍����A���̂��ߊC���痤�Ɍ������ĊC���������B��Ԃ͂��̋t�ŗ�����C�ɗ������������Ƃ͂悭�m���Ă���B�C���͎��C������A�����̉������܂�ł��邪�A�v�����N�g����אo�͂Ȃ��B�C�݂ł̑�C���ł͐V��ӂ����܂�A�S�����⌌�����㏸���S�x�@�\�����܂�B���g�Ȓn���̊C�݂͕ی쐫�C��A�k���̊C�݂͎h�����C��̂��Ƃ������B
�@�����͋C��h���ɂ悭�������A����ɓK������ƌċz�튴���ւ̒�R�͂����܂�B�h�C�c�ł͏����C�ǎx�b���▝�����]���̊C�ݗÖ@�a�@������B
�Q�j�@�����R�A���R�A�R�x�C��
�@�C���͊C�����x���n�\���100m�������Ƃ�0.6���ቺ����B���x��300m����1000m���炢�̍����A�����R�̋C��͊T���ĕی�I�ŁA���L���C��Ö@�̓K��������B1000m�ȏ�̍��R�A�R�x�ł͒�C���Ő����C���d�v�Ȗ����������_�▶���₷���B�אo�ʂ͏��Ȃ��A���˗ʂ⎇�O���ʂ������Ȃ�B�C������ƂȂǂ͓����Ɠ��A�̎Ζʂő傫�ȍ�������B�����������Ȃ艷�x��p�x�����܂�B�ሳ�A��_�f�̉e�����o�Ďh�����̋C��ƂȂ�B�����R�C��Ƃ����̒n��ɂ�����n�`�ω��𗘗p���āA�S�x�@�\�̃g���[�j���O�ɉ��p������B
�R�j�@�X�ыC��
�@�X�тɂ͋C��ɘa��p�����p������B������R�ہE�h����p��A���Í�p�̂���e���y���ނȂǂ̖F�������������U����Ă���A�������_�o�h�����̕��̋�C�C�I���������B�X�ѓ��̐Â�������t�̗ΐF�͐l�Ɉ��炬��^����B�X�ыC��͕ی쐫�̋C��ł���B
�@�X�ѓ��ł̓��ƂƓ��A�𗘗p������A�K�x�̍��x���𗘗p���Ă̕��s�^�@���͒n�`�Ö@�iTerrainkur�j�Ƃ��ĐS�x�@�\�̃g���[�j���O�ɓK���Ă���B
�\�|�S�@�×{�C��̓���
�C�m�C��
�����F�C���̊r�����A���x�������A�C�����ɊC���E���x���ܗL�A���O���̉e�����₷���B
�����F�V��Ә��i�A�����_�o�̈��艻
���R�C��
�����F��_�f�A��C���A�ቷ
�����F�C���͂������Ă������҂Ȃǂ̒b���ɉ��p�ł���B
���R�C��
�����F���R�C��قǒ�_�f�A��C���łȂ��h�������Ȃ��B �g���Ŏ��C�������B
�����F�x���j�i�V�N�ȋ�C�ɂ���C�Ö@�j �y�x�̏z�펾���Ȃ�
���n�C��
�����F�����A�C����œ��˂͍��R��菭�Ȃ��C���ω��͔�r�I���Ȃ��B
�@�@�@�X�ї��ł̓t�B�g���`�b�h�̍�p���W
�����F�x�{�A��J��
|
�i�R�j�C��Ö@�̓K���A�֊�
�@���a���Q���C�ۂ�C��Ɩ��炩�ɊW���F�߂���ꍇ�Ɏ��݂�i�\5�j�B�C��Ö@�ɂ������ẮA�C��h���ɑς�����\���͂�K�v�Ƃ���B�֊��ǂ͈�ʂɎ����̋}������\���͂̒ቺ���Ă���d�ǎ����ł���i�Q�U�j�i�\�U�j�B
�\�|�T�@�C��Ö@�̓K��
�P�D �����ċz�펾���F�A�����M�[���@���A�����C�ǎx���A�x�C��A�x���j
�Q�D �S�����̃��n�r���e�[�V�����iTerrain�Ö@�Ȃǁj�A�y�E�������x�̍������A�@�\���z��Q
�R�D �����_�o�����ǁA���a
�S�D �����畆�����i���]�A��ᝁA�_�o�畆���j
�T�D ���A�a�A�b��B�@�\���i�ǁA�������E�}�`������
�U�D �������n��
�V�D ���㎙���i����a�A�h�{�s���A�n���Ȃǁj
|
�\�|�U�@�C��Ö@�̋֊���
�P�D �V�N�ȐS�؍[�ǁA�]�����A�S�s�S�A�t�s�S�A�ċz�s�S�A�S�����A���x�̊��d��
�Q�D �}��������
�R�D �d�ǂȎ����A�����a�A�����n��
�S�D �d�ǂ̓����厾���A�S������A�A�W�\���a
|
�i�S�j�a�C�̔��ǁ@
�@�a�C�̔��ǂɂ͏h��v���i��`�A�N�߁A���A�̎��A�l��j�A�O�����v���i�C�ۊ��A�a���́A�L�Q�����A���́A�X�g���X�j�A�����v���i�H�����A�^���A�i���A�����A�x�{�Ȃǁj���֗^���Ă���B�i�}�P�j�������Ȃǂ̐����K���a�͐��F�̏�̕����̍��ʂ̈�`�q�Ɗ��Ƃ����������Ĕ��ǂ���B
�}�|�P�@���a���ǂ̗v��
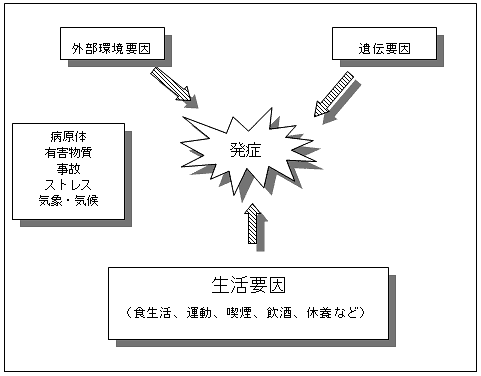
�i�T�j���ւ̓K��
�@���̂͊��̕ω��ɑ������_�o�n�A�����_�o�n�A������n�A�Ɖu�n����āA���̖h��\������B���͔̂畆���ւ��ĂĊO�������������������Ă���B�����ێ��ɏd�v�ȋ@�\�ɂQ����B�z���I�X�^�[�V�X�Ɛ��̃��Y���ł���B�z���I�X�^�[�V�X�Ƃ́A�������̍P�퐫��ۂ��߂̎������ߋ@�\�ł���A�Ԕ]�E�����́E���t�n����ɒS�����Ă���B
�@���̃��Y���Ƃ͋K���������������Č���鐶�̌��ۂ������B���̃��Y�������邽�߂ɐ��̂́A���ω��ɑΉ����ď�ɏ�����Ԃɂ���A�قȂ����h��������ƁA���̃��Y���Ɋ�����������ƁA�قȂ����h���ɂ�������������̍����댯�M���Ƃ��Ċ��m���A�v�����K�ɑ̒��𐮂��邱�Ƃ��ł���B
�@���̃��Y���̔����ɂ́A�O���̎������h���͑�ł��邪�A���܂�Ȃ���ɐ��̃��Y�������@�\�����݂��Ă���i���̎��v���邢�͑̓����v�j�B���v�@�\�͎�������j�A���ʑ́A�Ԕ]�|�����̂ɑ��݂��邪���̒����͎�������j�ɂ���ƍl�����Ă���B�ߔN�A�������v�̐U���@�\�Ɋւ����q��`�q���x���̌������i�W������B
�@���݂�͉���C��Ö@�����ꂽ���̃��Y���̐��퉻�ɗL�p�ł��邱�Ƃ��������Ă���B��ʂɁA���̓��O�̊��ω����h���Ƃ����̎h���������튯����e��ƌĂ�ł���B��e��́A�h���Ƃ��ẴG�l���M�[��_�o�C���p���X�i���j�ɕϊ����A���S���_�o���o�Ē����_�o�n�̊��o��ɏ��𑗂�B�h���ɂ͎�ށA�ʁA���̋�ʂ����邪�A�����e�킪����̎h���ɉ�������Ƃ��A���̎h������e��ɑ���K�h���Ƃ����B�Ⴆ�Ζڂɑ�����h���A���ɑ��鉹�h���������ł���B����ۗ{�n�ł͌܊���ʂ��āA���h�������͂���B
�i�U�j�C�ەa�ƋG�ߕa
�@�ȏ�q�ׂ��͉̂���ۗ{�n�Ƃ������Ǐ��̊��ɂ��Ăł��������A����ɍL���n���Ώۂɂ��ċC�ہE�C��Ƃ��炾�̊W�ɂ��Č������s���Ă���B���N�Ȑl�ł��C���G�߂ɂ���āA���_�I�ɂ��A�܂��g�̓I�ɂ��傢�ɉe������邱�Ƃ́A�N�ł��o������Ƃ���ł���B�a�l�̏ꍇ�ɂ͊��̕ω��ɂ��A���N�l���傫�ȉe������B�̂���C�ۂ̏�Ԃɂ���Ă���a�C�����a������Ǐ������邱�Ƃ́A�o���I�ɂ悭�m���Ă���B���Ƃ��A������̋C�ۂ̓��ɂȂ�ƁA�C�ǎx�b���̔��삪�N����Ƃ��A�Γ��ɂ�߂̒ɂ݂�i����a�l�͂��Ȃ葽�����A�t�ɂ��̏Ǐ�ɂ���ċC�ۂ�\�m�ł���l��������B���̂悤�ɋC�ۂ̏��������爫�e������a�C�|��������������ɔ��a���邢�͑���������́|���C�ەa�Ƃ�ԁB
�@����ɑ��āA�G�߂̈ڂ�ς��̎�����A����̋G�߂ɂȂ�Ƒ�������a�C��A�Ǐ�������a�C������A����͋G�ߕa�Ƃ���B�Ⴆ�Γ~�̂����A�Ă̏�����`���a�Ƃ������a�C������ɑ�����B
�@�������A�������̕a�C�́A�C�ەa�ƋG�ߕa�̗��҂̐��i�����˔����Ă���B�S�؍[�ǂ͈�ʂɓ~���ɑ����Ƃ���邪�A�č��̓암�Ɉʒu����_���X�ł͉Ċ��ɑ����B�l�͉Ăɂ͍������x�ɓK�����i���M�K���j�A�~�ɂ͊���ɓK�����Ă���i����K���j�B���x�����̃Z�b�g�|�C���g�͉Ăł͍����A�~�ł͒Ⴂ�B���̂��ߗႦ�������x�̐��ł��Ăł͗₽�������A�~�ł͒g����������B���̓K���𗐂��悤�ȋ����C�ەω��͋C�ەa�����������ƂɂȂ�B�������A�S�؍[�ǂ̐����͑����q�I�ł��艷�x����A���ω��A���댯���q�Ȃǂ��֗^���Ă���B
�@�C����̕ω��́A���ׂĂ̕a�C�ɑ��ċ��ʂ������ٓI�h���ł���B���̂͋C��h���ɑ��āA�����_�o�n�A������n�������Ċ��̕ω��ɑΉ����Ă���B���̋C��h�����t�Ɏ��Âɗ��p���邱�Ƃ�����B���ꂪ������×{�C��ł���B
�@�a�C���S�̋G�ߐ��́A�\�h����l�����ŏd�v�Ȗ��ł���B��������g�[�̕��y�ɂ�莾�a�̍D���G�߂̒E�G�߉����w�E����Ă���B
�i�V�j��w�C�ۏ��i�Q�V�j
�@�h�C�c�ł͈�w�ҁA�C�ۊw�ҁA�����w�҂̘A�q�̂��ƂɁA��w�C�ۏ�o����Ă���B���h�C�c�̃n���u���O�ł�1890�N�ȗ��̋C�ۃf�[�^�Ɋ�Â���1952�N���A�y�������������A��w�C�ۏ�o����Ă���B���̗\��͕a�@�ƈ�ʂ̈�t�Ɍ����ďo�������̂ŁA�C�ۑ䂩����\����̂ł͂Ȃ��A�a�@���t�̕����疈���A�荏�ɋC�ۑ�ɓd�b�Ŗ₢���킹�邱�ƂɂȂ��Ă���B
�i�W�j����ۗ{���ʂ̕]��
�@����ۗ{���ʂ�]�����邽�߂ɁA���̑O��ɂ����ĐS���e�X�g�i�S�g�̌��N��Ԃ̍���AQOL�]���A���Ɍ��ʁj�A�Տ��������s���B�����̎�ށA���@�ɂ��]���̐��x�͈قȂ�B
�@��ʌ����Ƃ��ĕa���A�����o�Ǐ�A�g���A�̏d�A���́E���͂̌����A�����w���ʐ^�A�S�d�}�A�o�C�^���T�C���i�S�����A�����A�ċz���A�̉��j�A�n�������i���F�f�ʁA�Ԍ������j�A�̋@�\�����iGOT�AGPT�Ar-GTP���̑��j�A�������������i���R���X�e���[���AHDL�R���X�e���[���A�g���O���Z���C�h�j�A�����A�A�����Ȃǂ���������B
�@����ɏڍׂȕ]���̂��߂ɂ́A���̂悤�Ȍ���������i�Q�W�j�B
�@�S�@�\�A���s���ԁi�S�G�R�[�}�A�X�����E�K���c�J�e�[�e�������j
�@�^���ϗe�\�i�^���������j
�@���퐶�����̕s�����A�S�؋����Ȃǂ̌��o�i�z���^�[�S�d�}�j
�@�]�@�\�ifunctional MRI�j
�@�����_�o�i�S�d�}R-R�Ԋu�ϓ��j
�@������@�\�i�����A�A���J�e�R���~���A�����E�A170HCS�A17ks�A���̑��̃z�������A�M�V���b�N�`���j
�@�ċz�@�\�i�X�p�C���O�����A�s�[�N�t���[�������̑��j
�@�E���i�n�i�ؓd�}�Ȃǁj
�@�����d���i���g�`�d���x�A�z�����G�R�[�}�AABI�Ȃǁj
�@���n�E�ÌŔ\
�@��J����i�t���b�J�[�e�X�g�j
�@�Ɖu�i�Ɖu�זE���A�Ɖu�זE�������A�T�C�g�J�C���j
�@���̃��Y���i���Ԑ��̏��̌����j
�@��L�̎w�W��p���ĉ��A�ۗ{�n�Ö@�̗L����������Ă���B�Տ������@�̐i���͒������A���㉷��ۗ{���ʂ̕]���͂���ɐ����ɂȂ邱�Ƃ����҂����B����ۗ{���ʂ͕��G�ł���A���G�n�Ɋւ��鐔�w�I��@�̉��p�����҂����B
�R�@�ۗ{�V�X�e���͎��ۂɂ́A�ǂ̂悤�Ȍ`�Ŋ��p�����ׂ����B
�i�P�j�ۗ{�V�X�e���̗��p�@
�@����܂ʼn���ۗ{�n�Ɋւ��ẮA�������̖{���o�ł���Ă���B
�i����Ö@��̂����߂閼���S�I�i�哇�ǗY�j�A�铒�Ɖ���Ö@�i�����Ёj�A�����ۗ{����n�K�C�h�i�����j�A�×{����̗��i�R�ƌk�J�Ёj�ق��j
�R�����i�V�����Ɂj�͂��ߑ����̕��l������I�s�������Ă���B�����̏��𗘗p������A����Ö@���A�h�o�C�U�[�ɑ��k�����肵�āA�x�{�E�ۗ{�̂��߂Ɏ����ɓK��������n��I�Ԃ��Ƃ��ł���B���̂����A���n�����ƌb�܂ꂽ���R��D�悷�邱�Ƃ���ł���B
�@�×{��ړI�Ƃ���Ƃ��́A�K���Ȑf�f�A���Âƕ]���A�\�㔻�肪�ł���a�@�����݂���A���S�ł���B����×{�ɂ́A�]������ˑR���Ȃǂ̏d��ȍ����ǂ������肤��̂œ��ɂ����ł���B���a�U�N��B��w���Êw���������n������Ĉȗ��A��w�����̉��Êw�̌��������S���e�n�ɐݗ����ꂽ���A�ŋ߂Ɏ���ꕔ�������ĕ����ꂽ�B��������Ë@��╪�͖@�̔��B���������A�܂�EBM�iEvidence
based medicine �����Ɋ����Áj���d�v������Ă��鍡���A����ۗ{���ʂ̉Ȋw�I�����́A����ɏd�v���𑝂��Ă���B����A���Ԏ哱�Ō����̌p�����W�����҂����B
�i�Q�j�ق�Ƃ��̉���Ƃ́i�Q�X�A10�j
�@�ŋ߁A����̖{���A�ی�A���p�����ƂȂ��Ă���B���s�̉���@�ł́@1�j�̎掞��25�x�ȏ�i���̓y�n�̕��ϋC���j�A2�j19��ނ̐����̂����ꂩ�����ʊ܂܂��A�̂ǂ��炩�ɂ��Ă͂܂�Ή���Ə̂��Ă悢���ƂɂȂ��Ă���B����������̖{���́A�n������N�o���鐅�ŁA���ʂȉ��w�����g���╨���I�����������A��w�I�������ʂ������炷�\��������u�z��v�ł���B����̌��_�́u����v�ɂ���B����Ƃ́A�n��ɗN�o���������̂��̂������B
�@�ߔN�A�Z�p�̐i���ɂ���[�x�@��i1000m�ȏ�j���\�ƂȂ��Ă��邪�A�ʂ����Ĉ�w�I���ʂ�����̂��A�ώ����Ă��Ȃ��������ł���B
�@���̗ʂɂ͌��肪����B�@�肷����Ɖ���̌͊���������B�����̒ቺ�A���ʂ̒ቺ���������B�����߂���ƓK���܂ʼn��������B�����K�͂��傫���Ȃ������D�̓��ʂ��m�ۂ��邽�߂ɁA������u�z���v�̕������Ƃ�����B�����h�~�̂��߉��f�ɂ��E�ۂ��s����B
�@����A��������œ����g�p�����o���Ĉȗ��A�������̎g�p�A����̖������p�܂ŁA����Ɋւ���s�K���ȗ��p��\�������X�Ɩ��炩�ɂ��ꂽ�B�����͏����J�̕s�O��A����ɊW�҂̃������ቺ�ȂǁA���܂��܂ȗv�f���d�Ȃ��Ă���B
�@������܂��邽�߂ɂ͋ƎҁA���p�ҁA�s���ٖ̋��ȘA�g���]�܂��i�ØI���F����16�N�����V���j�B
�@���ł��邪�A�啪�����R���ۑS�ψ����ł́A�����N�o�ړI�̓y�n�@��A����y�ѓ��͑��u���̋��\���̐R�c�́A���v��K�v�Ƃ���ꍇ�������A���ʕی�n��ɂ����ẮA�@���F�߂Ȃ��A�ی�n��ɂ����Ă͐R�c��Ɋ�Â��K�����s�����ƂɂȂ��Ă���B�܂�50�N���A�������������ɂ��Ēn�w�A��w�A�@���ȂǑ��ʓI�Ȍ������\�𑱂��Ă���B
�@�啪���ł͖��ԋƎ҂ɂ�艷�����b������������A���p�҂ɕ�����₷������\���݂̍����T���Ă���B�����̒��x�A�������̓��̕��z�A���̓����A�����I�ȕ]���Ȃǂ����肱�ނƂ��Ă���B�܂��ʕ{���كz�e���g���A����ł́A����̐����Ƌ��ɗ������̓��̐�����\������\��ł���i����16�N�啪�����V���j�B
�i�R�j���Ԋ��͂̏d�v��
�P�j�@�t�B�b�g�l�X�N���u���̑�
�@���Ԏ��Ǝ҂𒆐S�Ɍ��N�Â����W�Ԃ���t�B�b�g�l�X�N���u�A�A�X���`�b�N�N���u�Ȃǂ̉^���{�݁A�N�A�n�E�X���p�ɂ�錒�N�Â����ۗ{���s���{�݂̐������s���Ă���B1988�N�����J���Ȃ́u���N���i�{�ݔF���i�����ȍ�����273���j�v�����\���A�{�o�c�҂̐\���Ɋ�Â��A�����J����b���F����s�����x���������B
�Q�j�@�R�z�@�̏ꍇ�i�Q11�j
�@�R�z�@�͖~�n�ŁA�c�ɂł���A�������Ղ��Ȃ��B����̗N�o�ʂ͑S�����ʂƂ����L�x�������q�͏��Ȃ������B���������݁A��������n�̂Ȃ��Ńg�b�v�N���X�̐l�C���W�߂�悤�ɂȂ����B�N�Ԃ̊ό��q��380���l�A�h���q��95���l����܂łɂȂ��Ă���B���̐����̔閧�́A���Ԏ哱�̂܂��Â��肾���łȂ��A�s������̂ƂȂ��ċ��͂������Ƃɂ��B�R�z�@�̎��R����邾���łȂ��A�u�����̗R�z�@���l�����v�������A�Y�Ƃ���ĂāA����L���ɂ���A�����������Ɗ�������A�Ȃ��₩�Ȑl�ԊW������Ȃǂ̂R�̂��ƂɎ��g��ł����B�S���t��̌��݂��������A���a34�N�ɓ��z�@�́u���N�E�ۗ{�E����n�v�Ɏw�肳�ꂽ�B���̂悤�ɂ��ėR�z�@�͉����Ǝ��R���Ɍb�܂�A���y�I�F�ʂ̂Ȃ����N�I�ȉ���n�ƂȂ����B�R�z�@�ł́u�����̂��钬�Â�����v�ɂ��A�R�z�x���ǂ�����ł�������悤�Ɍ����̍������K�����Ă���B
�R�j�@�ʕ{����������
�@�ʕ{�A�l�e�A�ϊC���A�x�c�A���H�A�ĐA�S�ցA�T��̂W�̉����琬��ʕ{�����ɂ́A���ꂼ��̉����ƂɓƎ��̕������A���̘Ȃ܂���������قȂ��Ă���B�I���p�N�͕ʕ{����������̗��̂ŁA�ʕ{���������Ɂu����v�u���N�v�u�H�v�u�E�H�[�L���O�v�Ɋւ���v���O������̌����Ȃ��牷����Ĕ������鉷������s���Ă���B���N��H�ɂ��Ċw�сA�y���݂Ȃ��猳�C�ɂȂ��10���Ԃ���{�Ƃ���B�܂��A���̌��ʂ��A�����x�̓_����]�����悤�Ƃ��Ă���B
�ނ���
�@��[��w�͕��q�����w�A��`�w�̔��B�ɂ��A�a�C�̖{���I�������\�ɂ��A�l�̈�`���Ɋ�Â��A�œK�̎��Â��s��tailor-made
medicine��ڎw���Ă���B����A����ۗ{�n�w�́A���R���h���𗘗p���āA�S�l�I��Â����݂�B���҂͑��₢�A�l�̋ꂵ�݂��Ƃ�A����������^���铝����ÂƂȂ邱�Ƃ����҂����B����ۗ{�n�̕ۑS�́A�ŋߖ��ƂȂ��Ă�����j��A���g���A�ЊQ�A���q����A��Ìo�ς̔j�]�ւ̑�Ƃ��Ė𗧂\��������B
�Q�l����
�P�j�A�c���F�@���N�ۗ{�np.8�`9 ���C�ۊw�̎��T�@���q���X1992
�Q�j�������R�ی�NJďC�@����K�g�@p.56�`60 ���{����@1995
�R�j���q��v�ďC�@��҂������߂���ق̉���@���w�� 2001
�S�j��ˋg���@����Ö@�@�����ւ̃A�v���[�`�@p.104�`116 ��R���@1999
�T�j�哇�ǗY�@�]�n�Ö@�|���_�|�@������Mook14 �C�ۈ�w
�@�i�n���Y��ҏW�jp.104�`107�@�����o�Ł@1980
�U�j���ݗS�K�@�C��Ö@�@���C�ۊw�̎��T�@p.2�`3 ���q���X�@1992
�V�j�ЎR�@�I�m�d��@��w�C�ۗ\��@������Mook14 �C�ۈ�w
�i�n���Y��ҏW�jp.173�`185�@�����o�Ł@1980
�W�j���X��M�ق��@����̈�w�̈�ւ̉��p�Ƃ��̕]���@p.12�`20 �V�����w�@�@���{����C����w��@2004
�X�j�ΐ엝�v�@����@���@�@�W�p�� 2003
10�j���c���� ����́A����ł͂Ȃ� �����̉���[�~�i�[���Q�@
�����Ё@2004
11�j�ؒJ�@���O�@�R�z�@�̏����Ȋ�Ձ@�V���� 2004
|



