|
1 温泉保養地のマーケティングとは
(1)マーケティングの定義
マーケティングの概念は20世紀初めのアメリカ自動車産業で生まれたと言われている。T型フォードに見られるように大量生産により需要を上回る供給が可能になると、販売の停滞が起き、生産活動も停滞する。企業収益を維持するためには、商品に新しい価値を与え、複数購入や再購入を進める必要がある。これを最初に行なったのが、後発のジェネラル・モータース(GM)のスローンであった。自動車王ヘンリー・フォードは、消費者は複数のT型フォードを購入するだろうと予測してモデルチェンジを行なわなかったが、一方、スローンは高級車のキャデラックから、中級車ビュイックやポンティアック、そして大衆車のシボレーとフルライン政策を取り、消費者の幅広いニーズに対応するとともに、毎年モデルチェンジと大量の広告・宣伝を行ない、消費者に買換えメッセージ(心理的な製品陳腐化戦略)を送った。この結果、選択肢のないT型フォードのユーザーはそれぞれ好みのあったGM車を選ぶことになり両社のシェアは逆転した。爾来、GMが全米自動車産業の頂点に立っていることは周知の通りである。
このGMの事例にも既にいくつか採用されているが、今日、マーケティング活動の要素として「3C・4P」が重要と言われている。これは各要素(図表−1)の頭文字をとったものである。
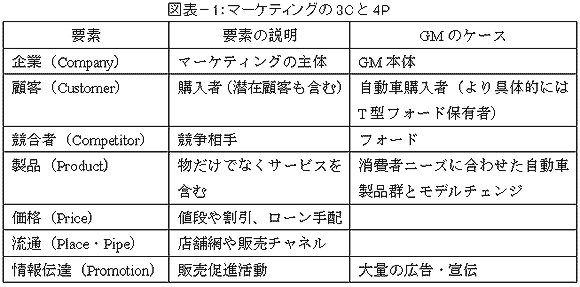
また、最近ではこの他に、人的資源(Person)や情報・システム(Communication)も要素に加える人もいる。
なお、アメリカ・マーケティング協会(AMA)では以下のように定義(1985版)している。「マーケティングとは、個人と組織の目的を満足させる交換を創造するために、アイデア・商品・サービスについての、概念形成・価格設定・プロモーション・流通を、計画し実施する過程である」
実際のマーケティング活動において、マーケティング主体(企業や団体)は、こうした要素を有機的・機能的に組み合わせ、顧客に価値(効用や満足)を提供することで、自社の利益やマーケットシェアの増大を図る訳であるが、それぞれの立場(ポジション)や環境・制約条件などにより取るべき方法は異なる。例えば、前述のGMはフォードを追いかけるチャレンジャーという立場であったため、価格重視路線(同一車種の大量生産による低価格化)を取るフォードに対し、製品差別化と商品陳腐化メッセージ(情報伝達)に力点を置いたマーケティング戦略を採り成功を収めた訳である。
なお、マーケティング活動は、供給(生産)が需要(消費)を上回っている環境と顧客ニーズ・ウォンツが存在することが前提になっている。このため、競合状況も含めた市場環境や顧客・消費者ニーズをあらかじめ収集・分析することが取るべき最初の行動となる。これを図示すると図表−2のようになる。
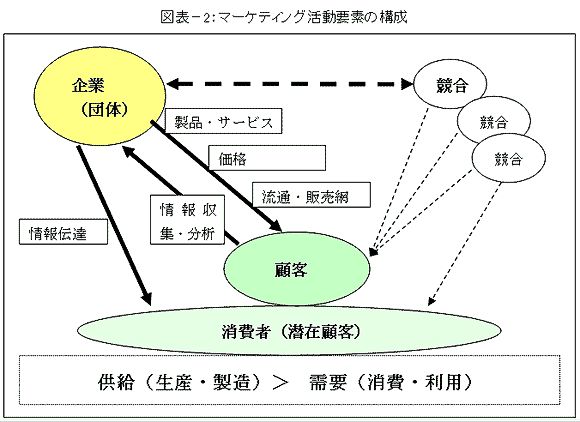
日本の温泉地についてみれば、高齢者を中心に根強いニーズがあるが、その一方、週末や年末・年始、ゴールデンウィークを除けば、どの温泉地も空室が目立っている。また、近年余暇活動が多様化しており、温泉地を訪れる人は長期的に減少している。すなわち、ニーズがあるにも拘わらず、供給過剰な状態でかつ競合が存在するというマーケティングが必要な状況にある。では、製品・サービスの差別化や広告・宣伝などのマーケティング活動がなされているかと言えば、一部の温泉地を除けば、いずれも同じような内容・価格の一1泊二食型宿泊サービスの提供であり、マーケティングがなされているとは言い難い。これは、温泉宿泊施設が比較的小規模で家業的経営であるためとも考えられるが、今後「企業」として脱皮するためにマーケティングの視点は必要不可欠である。
(2)マーケティング主体
製造業者や流通業者など個々の企業が他社との競争に打ち勝つためマーケティング活動を実施するのと同様に、温泉施設や旅館・ホテルなど個別の事業体がマーケティング主体となる。しかし、一般的にこうした事業体は小規模経営が多く、知識や費用の点で単独での実施は難しいため、観光協会、温泉(旅館)組合などの団体や自治体がマーケティング活動を行なうこともある。温泉地やリゾート地の場合、その地域や環境そのものが一つの商品となっていることから、団体や自治体がマーケティングを行なうこと有効であるが、その活動範囲は限定的である。例えば、団体では、イベントの実施や販売チャネルの開発、PR活動及び景観保全に関わる活動となる。また、自治体ができるマーケティング活動はPRや広告宣伝活動、交通や河川などのインフラ整備に限られる。図表−3はマーケティング主体別の活動範囲と期待効果である。
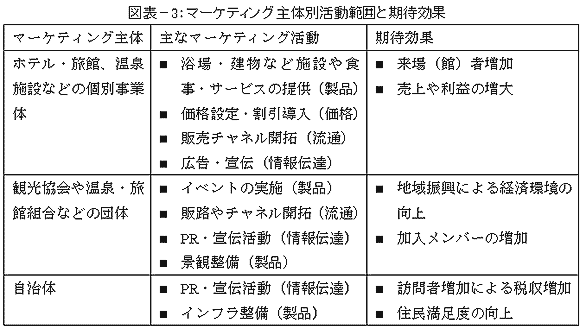
(3)基礎データの収集と分析
顧客や自分自身の強み・弱点、競争相手を知らずしてマーケティングを行なうことはできない。顧客がどのような人々で、どのような特性を持っているかなど顧客プロフィールや旅行行動に関する情報を収集するとともに、当該温泉地の評価や他の余暇活動の情報を収集・分析し、基本的な実態を把握しておく必要がある。このような基礎情報を持たずにマーケティングを進めても、独りよがりなプランになることが多く、せっかく投資をしても顧客からは評価されないという結果になってしまう。
顧客についての情報・データは宿帳などの取引データからも収集できるが、行動様式や過去の経験などはインタビューやアンケートによって集める必要がある。この場合、季節によって顧客特性が異なるケースもあるので、年に数回行なうべきであろう。また、必ずしも顧客全員に対してアンケート調査を行なう必要はないが、サンプル調査を行なう場合は対象者を無作為抽出する必要がある。
収集すべきデータは、図表−4のように顧客の住所や年齢から温泉の評価や余暇状況まで多岐に渡るが、基本的には5W1Hを念頭に置いて進めればよいだろう。

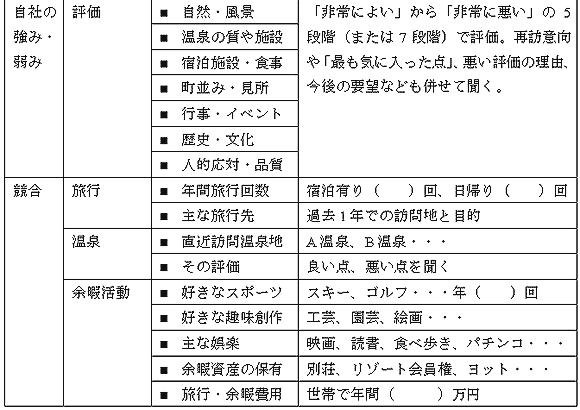
収集したデータを集計・分析することで主要な顧客のプロフィールが明らかになるほか、温泉に対する満足度(不満)から顧客が何を求めているが分かる。こうした情報に基づいて自社や自地域の強みを更に強化し、また弱みを改善することが可能となる。また、余暇時間の使用について競合する他の余暇活動の把握から魅力ある温泉地作りのヒントを得ることもできる。図表−5はデータ分析により得られる主な用途である。
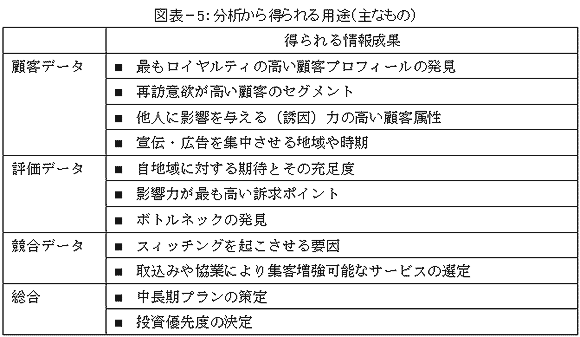
マーケティング主体が正確なデータや情報を得るためにはある程度の費用と時間がかかる。個別の温泉施設やホテル・旅館が調査を行なう場合は、従業員やスタッフを使ってインタビューを行うことで費用を抑えることもできるし、また顧客とのコミュニケーションを強化できるので有効な方法である。また、自治体や商工会または観光協会や温泉組合などの団体費用を負担できる組織が調査の実施主体となる。また、複数の事業主が共同で実施することも可能である。
調査の実施者は専門の調査会社が望ましいが、予算などの制約があって利用できない場合は、リサーチコンサルタントの指導を受け、現地の関係者が手作りで実施することで、ある程度精度を保ちかつ費用もそれほどかからない調査ができる。
(4)温泉地の歴史動向
個別にマーケティング要素を論じる前に、温泉地の歴史動向を概観しておくことは、現在の状況を分析する上で有効である。
日本の温泉地は「記紀・万葉」の時代からその存在が記されているが、温泉の開湯伝説の多くに、空海や役小角が発見したとか、傷ついた動物が湯につかって治すのを見たからという伝承が残されているように、温泉は人里離れた山間部や渓谷沿い、または海浜に湧いていた。また、治癒力という神秘性のため、為政者や修験者・山伏など僅かな人々にしか知られていなかったし、「信玄の隠し湯」のように所在地も秘密とされていた。それでも、温泉の効用は口伝えに広まり、政治が安定して往還が安全になった江戸時代以降は、農閑期や漁の端境期に農民や漁民が湯治に訪れるようになった。この時代の温泉利用は純粋に治療と保養であった。また、藩主の訪問をきっかけとして交通や宿泊施設が整備され始めた。しかしながら、当時は人の移動が厳しく制限されていたため、利用者は特権階級と近在の住民に限られていた。
江戸時代後期になると街道や宿場町が整備され、商人などが盛んに通行するようになった。一般の人々も「伊勢参り(おかげ参り)」など寺社参りが許されるようになると、「精進落し」と称して温泉で遊興するケースが現れた(伊勢参りの榊原温泉、蔵王権現参りの遠刈田温泉、善光寺参りの戸倉上山田温泉など)。温泉旅行に「ハレ」と「遊興・歓楽」のイメージがついた。更に、明治・大正時代になり鉄道などで交通手段が整備されると熱海や箱根、有馬など大都市近郊の温泉地は大きく発展した。また、新たな泉源発掘もなされ、それまでの外湯式から各旅館へ引き湯する内湯式温泉施設が現れた。しかし、この時代の利用者の多くは政治家や裕福な商人であり、かれらは別荘を建て、保養地や避暑地として温泉地を利用した。また、ドイツ人医師ベルツ博士が温泉を医学として取り上げたのもこの時代である。このことから温泉のイメージに「高級感(ハイブロー)」「治療」のイメージが持たれるようになった。
温泉が真に大衆化したのは戦後になってからである。朝鮮戦争特需に始まる戦後復興期、その後の高度成長期を通して企業は潤ったが、それは勤労者の賃金や福利厚生制度が相対的に低く押さえていたためであり、また労働争議が頻発するなど雇用状況も厳しいものであった。こうした状況下で企業は、職場でのストレスを軽減する手段として、また、終身雇用・年功序列・家族主義の日本型経営手法を強化する手段として、会社(職場)ぐるみの団体旅行を実施した。旅行積立や会社補助が行なわれ、「組織の和」の名の下に全員参加という半強制の行事であった。企業の生産性を落とすことは許されないため、土曜日の午後に会社の前からバスを連ねて出発し、温泉に入るのもそこそこに大広間での宴会となった。「無礼講」が職場のガス抜きとして使われたり、男性向け歓楽サービス施設へ繰り込んだり、いわば「オルギー(秩序の破壊)から再生」という再生神話にも似た状態が繰り広げられた。そして翌日曜日にはお座なりな観光を行い、夕方疲れて帰るのであった。旅館側も、こうした1泊宴会型団体旅行ニーズ(多くは旅行代理店からの要請)に応えるため、競って増築や新館建設を行なった。ニーズは単純でボリュームも大きいため、どの旅館も建物から食事内容までほぼ同じ内容で、企業と同じ大量生産・大量消費が貫徹されていた。従って、お客をどう効率よく捌くかが課題であり、差別化などのマーケティングニーズは存在しなかった。こうした状況が1955年頃から石油ショックが起きた1970年代中期まで続いたが、この時期の設備投資や経営方法はその後長く旅館経営にとって重石となった。しかし、こうした団体旅行により初めて温泉を体験した人も多く、その後の温泉ブームを支える基礎となっていることも見逃せない。
70年代は石油ショックの影響と団塊世代の個人主義的傾向で職場団体旅行も大きく減少した。しかし、「ディスカバージャパン」や「アンノン族」などメディアのキャンペーンに乗る形で若い女性を中心としたグループ・個人旅行が新たに台頭してきた。彼女たちは「おじん趣味」と揶揄されつつも、職場団体旅行ブーム時には見向きもされなかった、鄙びた温泉地や秘湯の露天風呂を楽しむことを覚えた。もちろん、テレビや女性週刊誌の特集というマスコミの影響力によるものであるが、若い女性の温泉指向は、その後「ナイスミディ」と呼ばれた中年女性のグループ旅行に引き継がれ、料金が割安な平日の日帰りまたは1泊で温泉を楽しむ旅行が根付いてきた。彼女たちこそ職場旅行で宴会に辟易しながらも温泉の楽しみを覚えた最初の世代であった。こうした流れの中で2001年には温泉は、これまで国内旅行でトップであった周遊観光からその座を奪うまでに至ったのである。さらに、近年では職場や家庭でのストレスからの「癒し」を求めて各年代の個人や小グループの客が温泉地を訪れるようになっている。
以上、温泉地と利用者の歴史的な流れを見てきたが、大きな流れとして
1.特権的利用者から一般利用者(大衆・個人)へ
2.単一利用目的(湯治)から多目的利用へ
という、2つの潮流があることが分かる。今後ますますこの傾向は強まると予想されるが、こうした流れに温泉地としてどのように対応するかが大きな課題となろう。
2 商品(サービス)と価格
(1)顧客二一ズ
消費者の温泉地(温泉施設や旅館・ホテルなどを含む)に対するニーズは、図表−6のように医療から休養・保養、観光や運動、そして社交や歓楽までと非常に多岐に渡っている。
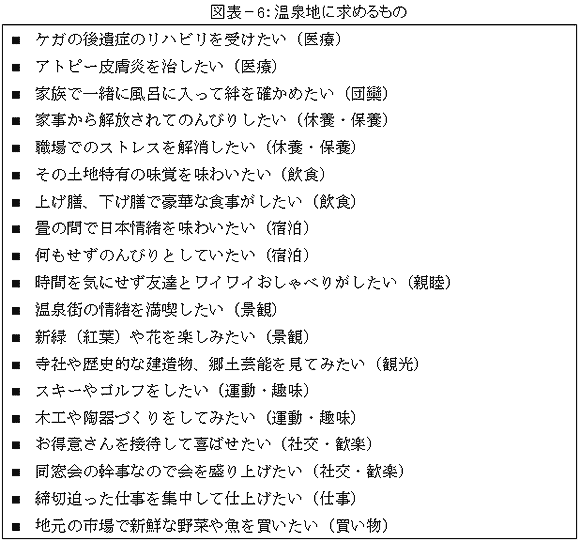
この他にも様々な希望やニーズがあるだろうし、また一つの目的だけでなくいくつかの複合ニーズもあるだろう。まさに、十人十色、むしろ「一人十色」といった多様なニーズが存在している。
また、こうしたニーズは均一的に存在するのではなく、訪問客の年齢層や性別、所得や教育水準、居住地や職業・職位、更には価値感や趣味によって特定のニーズに偏る傾向が見られる。例えば、(財)日本交通公社の旅行者動向調査「旅行者動向2004」によれば、温泉地で体験したいこととして男女とも「全身マッサージ」をトップにあげているが、年齢層によって異なっており、20代男性と40〜50代男女では「全身マッサージ」のリラクゼーションを第1位としているが、20代女性は「フェイスとボディのエステ」と美容指向が高くなるし、一方、60代以上の男女では「温泉浴による治療」がトップとなり、療養意向が強くなっている。この結果は全国平均だが、当然、訪れる温泉地によってまた違った結果となるかもしれない。
しかし、消費者の多様なニーズに対して、果たして温泉地は十分な対応を行なっているだろうか。勿論、新しい取組みを行なっている温泉地もあるが、大半の温泉地では1泊2食を基準とした宿泊や宴会パックなどのセットメニュー的なパッケージ商品しか提供されていないのが現状である。こうした画一的な商品は、大量生産・大量消費的な職場団体旅行が中心であった時代には経済効率性の高い有効な商品であったが、人々が豊かになり、様々なニーズを持つようなった今日、「帯に短し、襷(たすき)に長し」で十分にニーズを満たしているとは言い難い。人々の余暇活動の中で温泉指向が高まっているにも拘わらず、温泉地が全体として衰退している原因の一つに消費者ニーズに対応できていないことがあげられよう。
(2)商品(サービス)の構成要素
さて、前述の通り温泉地や温泉施設に対しては様々なニーズがあるが、こうしたニーズに対応する商品・サービスとして、「泊」、「食」、「浴」、「遊」の4種類のサービスに括ることができよう。この内、「泊」、「食」、「浴」サービスについては、一般には旅館など温泉宿泊施設がセット(特に「泊」と「食」)で提供し、「遊」については、温泉地や周辺地域の企業・団体が提供するという構図になっている。(図表−7)
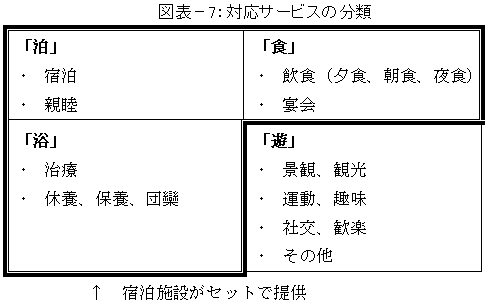
一方、それぞれのサービスカテゴリーについて提供者(サービスプロバイダー)を見ると、図表−8のように「泊」、「食」、「浴」サービスについてはその種類は少ない。一方、「遊」については様々な業種や規模の異なる企業が参加しており、提供するサービス内容も豊富である。
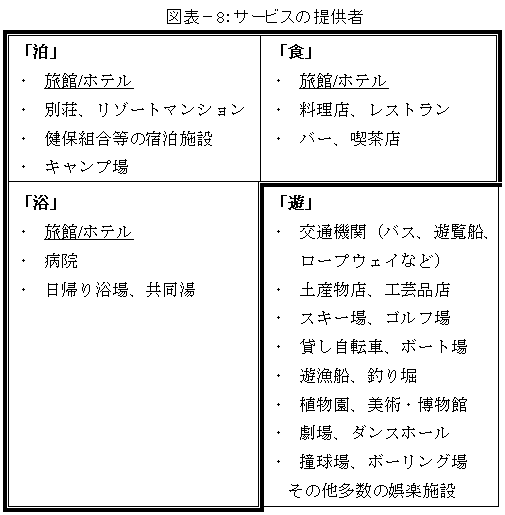
上記の図表の通り、「遊」については多種多様なサービスがさまざまなプロバイダーから提供されているが、「泊」「食」「浴」については特定の提供者(旅館やホテル)に限られている。サービス間にこうしたアンバランスが生じるのは、サービス提供者間の競争状況の違いによると考えられる。すなわち、旅館やホテルはいったん訪問客を取り込めば、施設内に止め置く限り他の競争者から隔離でき、安定した収益を確保することができる(施設内に土産物店やカラオケ、バーを設置したのは宿泊客を外出させず、他の競争相手に晒させないためであるが、そのため温泉街全体が寂れる原因ともなっている)が、「遊」を担うサービスプロバイダーは、旅館・ホテルから出てくる数少ない客を獲得するため競わなければならず、このため多様な商品やサービスが生まれたと考えられる。なお、宿泊施設は一般にサービス部門毎の事業収支を取っていない(いわば「丼勘定」)であるため、部門間の競争もなかったと考えられる。
温泉地の宿泊施設では、多様性のない「泊」「食」「浴」サービスがいまだ一般的であるが、訪問客の多くが住む大都市ではこうしたサービス分野に対して既にバラエティ溢れるサービスが提供されている。例えば「浴」であれば、イベント性のある日帰り型温泉テーマパークがあるし、フィットネスセンターでは水中ウォーキングやアクアビックスなどを運動プログラムとして提供している。また「食」についていえば、フランスからアフリカまで世界の料理が食べられ、コンビニでは24時間暖かい食べ物を買うことができる。更に「泊」ではアーバンリゾート型ホテルの豪華な客室からカプセルホテルまで、数10分のお昼寝ルームからウィークリーマンションまで、実に多種多様な「泊」サービスが提供されており、それぞれに顧客層を確保している。
都市で多様なサービスをエンジョイしている消費者は温泉地においても当然同等以上のサービスを望むはずであるし(地方の消費者であってもメディアの影響で都市住民と同じ程度の情報を持っている)、訪れた温泉地や宿泊施設で選択肢の少ないサービスしか受けられないとしたら、彼らの期待は萎み、満足度も高くならないであろう。サービス利用経験の豊かな「目の肥えた」消費者を満足させ、ファン化するためには「泊」「食」「浴」分野のサービスを多様化し、充実して行く必要があろう。図表−9は、各カテゴリーについて可能なサービスメニューの一例であるが、各サービスの組合わせや創意工夫によって下記以外にも様々サービスが考えられるだろう。なお、「遊」については多種多様なサービスが既にあるため、掲載しなかったが、今後は高齢者の知的関心や好奇心を満たす「学び」を中心とするサービスが現れてくるだろう。
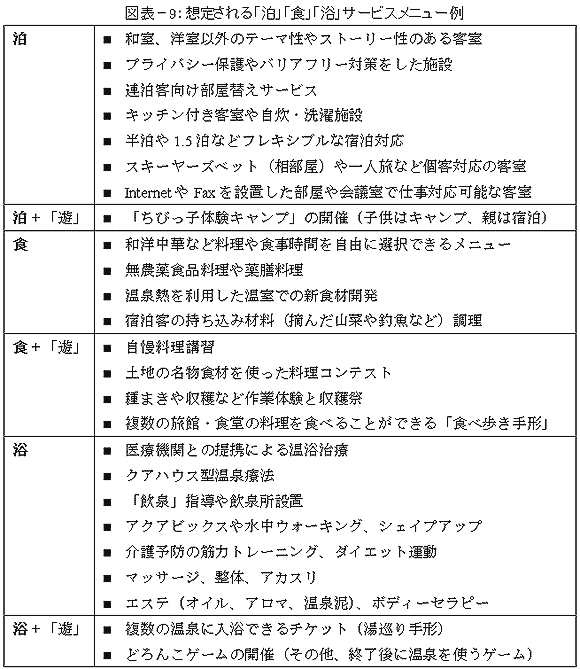
(3)選択と集中
前節では、温泉地や温泉施設に対して消費者は多様なニーズを持っているが、現在はそうしたニーズが十分に満たされているとは言い難い状況にあるものの、温泉サービス提供者の努力と創意工夫によって商品・サービス開発ができればニーズを満たす可能性があることを見てきた。しかし、消費者が要求する全てのニーズに対応することは資源の制約上不可能だろうし、仮にできたとしても、個々のサービスは底の浅いものとなってしまい、サービスの利用経験豊富で旅慣れた消費者からは「幕の内弁当」的なサービスとして早晩に飽きられてしまうだろう。こうした全方位的なサービス開発は、結局、何でも取り込んで肥大化し、経営不振に喘ぐ大型宿泊施設の二の舞となることは想像に難くない。
では、こうした要求度の高い消費者を飽きさせず、魅力あるサービスを作るにはどうすればいいだろうか。まず「一泊二食」に代表されるプロバイダーオリエンティド(供給者中心主義的)な考え方をカスタマーオリエンティド(顧客中心主義的)に切替えることはもちろんであるが、顧客を知り、かつ自地域の強みについて十分な洞察を持つ必要がある。そして利益をもたらす顧客が誰かを発見し、彼らの満足度が最大になるような差別化されたサービスが何かを検討することになる。この場合、図表−10のように要素毎に検討すると整理しやすい。また、顧客情報については「基礎データの収集と分析」(第1章第3項)で述べたアンケートなど調査結果をベースに検討するのが望ましい。
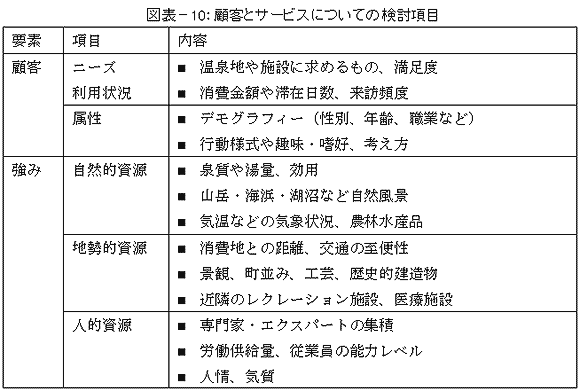
日本には温泉地は約3,000個所もあり、(隣接する一部の温泉地を除いては)環境や顧客条件、強みはそれぞれ異なっている。このため、誰をターゲットとし、どんなサービスを提供すべきかについてはそれぞれの温泉地で様々であり一般化はできない。しかし、理解を助けるために単純化した温泉地Aの事例(図表−11)で説明してみよう。
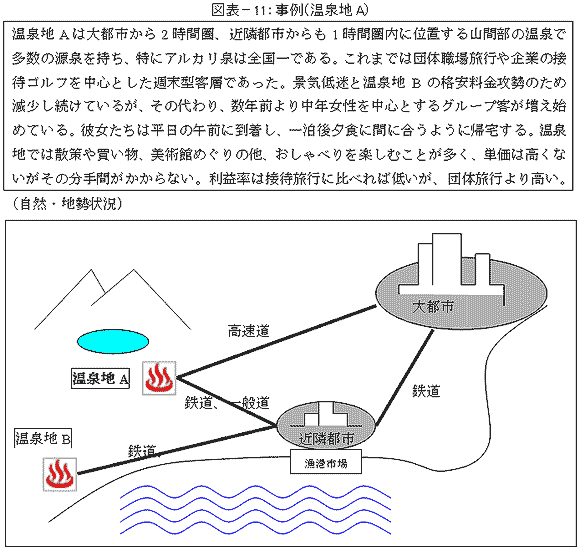
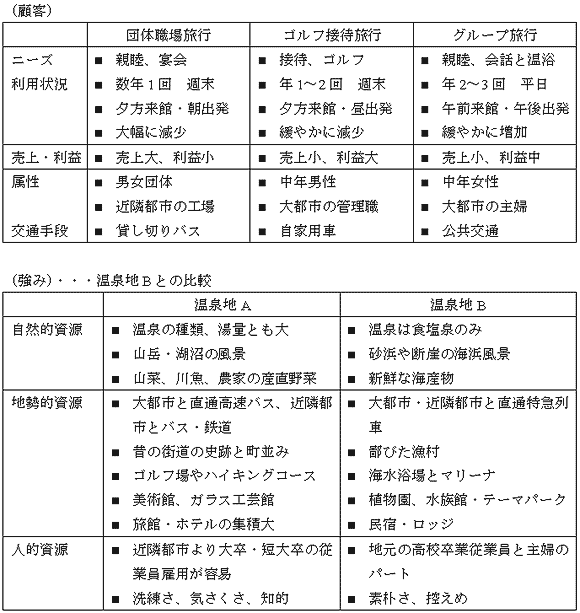
[ターゲットの選定]
上記の事例で、3種類の顧客群の中で「中年女性のグループ客」をターゲットに選んだ。その理由は以下の通りである。
・ 宿泊客の少ない平日の室稼働率を向上できる。
・ 団塊の世代であり、ボリュームゾーンを構成している。
・ 口コミ効果が期待でき、比較的豊かな大都市生活者を吸引できる。
・ アルカリ泉の美容効果や森林浴の癒し効果を訴求できる。
・ 無農薬・有機栽培の食材が安定的に入手でき、健康ダイエット食でアピールできる。
・ ガラス工芸やハイキングなど比較的安価な余暇・娯楽活動を提供できる。
・ 将来、定年退職後の夫を同伴した余暇活動としての来訪が見込める。
[サービスの選定と集中]
「中年女性のグループ客」をターゲットにした場合、温泉地や宿泊施設が持っている強みを生かし、彼女たちのニーズを満たすサービスを強化する必要がある。「泊」「食」「浴」「遊」毎に温泉地A(の宿泊施設)がどのようなサービスに集中すべきかを考察した。
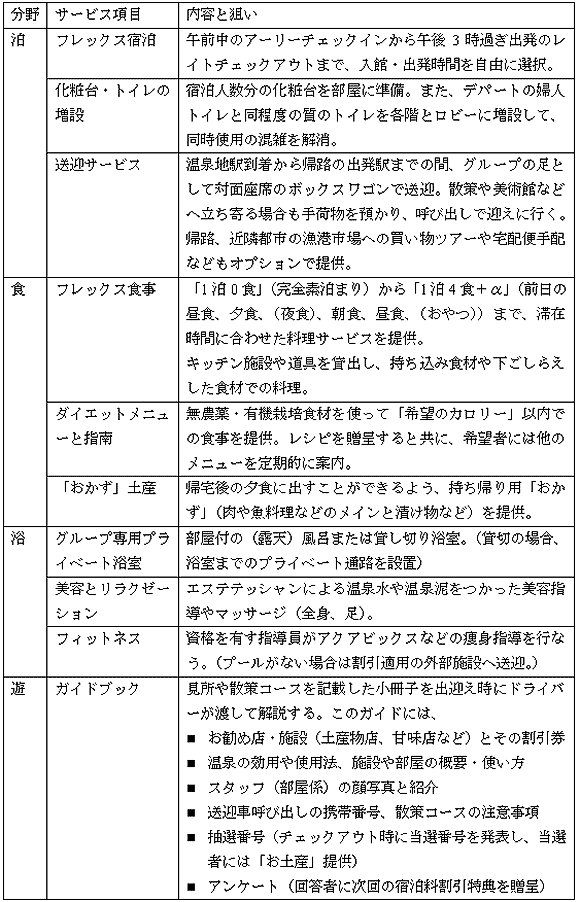
上記のターゲット客や強化するサービス例は仮説であるが、実際に設定を行なう場合は各部門のスタッフと綿密な打合せを持つと共に、顧客に直接インタビューして利用意向を確認する必要があるだろう。また、マイケル・ポーターが教えるように、「他とは異なった製品、サービスを提供し、顧客にその違いを認知してもらい、競争上の優位性を築こうとする差別化戦略」が有効であるが、サービスにおいては特許や商標登録による保護がないため、真似られやすい。このため、その土地にしかないものや特産品をサービス作りに活用してユニークさや優位性を確保すべきであろう。例えば、西表島(沖縄県)は山猫で有名だが、長崎県に「対馬山猫」が生息するため、山猫を「日本唯一」とすることができず、代りに東経123度45分67.89秒の並び数字の子午線が日本で唯一、島内を通過していることから「子午線マラソン」を企画・実行して島興しを行なっている。こじつけに近い「日本唯一」であるが、他がコピーできない点で学ぶことが多い。
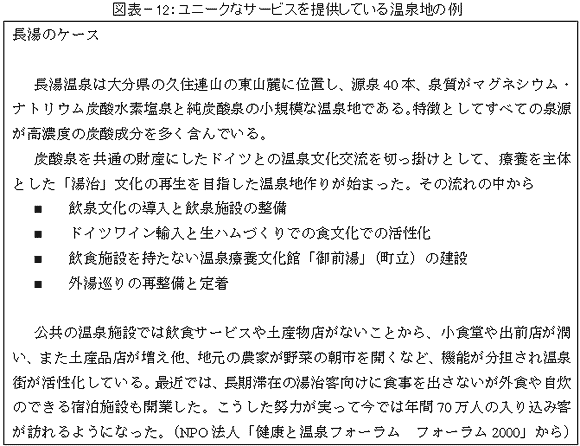
長湯のケースは、高濃度の炭酸泉という「ここでしかない資源」を使った「飲泉」文化を育て、湯治客や健康志向の観光客を吸引するほか、更に「泊」「食」「浴」を機能分化することで地域(温泉街)産業を活性化させている。旅館や飲食店がメンバーの観光協会の熱意とマーケティングが功を奏したものである。
(4)価格戦略
価格を決定する方法として「コスト発想」と「市場発想」があるが、前者は材料費や人件費などの製造原価に利益を乗せて決める方法で、主にテレビや自動車のような工業製品で多く見られる。一方、後者は市場の需給状況や競争相手の価格を参考に決定するもので、農産物や鮮魚のように市場で競りにかけられて決まる価格である。サービス商品の価格は目に見えるような「市場」や「競り」はないが、温泉地や宿泊施設という供給者と訪問客という需要者の間で「満足度」を交換尺度にして決まるものであり「市場発想」型である。もちろん施設・設備の減価償却費や人件費、食材費など原価となる費用はあるが、どんな安い価格でも顧客が満足を得られなければ購入はなされない(実際にはサービスを受ける前に支払っているので、正確には「次回の購入はない」ことになる)。反対に、期待以上の満足が得られれば、原価を遙かに超える金額が「再訪や口コミ宣伝」の形で支払われる。従って、売り手が利益をあげるために、メーカーが製造コスト削減を行なうのに対して、サービス供給者は買い手の満足度を増大にするよう努力することになる。
一方、買い手は絶対的な「満足度基準」を持っている訳でなく、これまでの経験や情報収集により、特定のサービスについて期待水準とそれに見合う価格を事前に想定し、その範囲に入るサービスを購入(予約)する。満足が生じるのは、価格に比して期待水準以上のサービスが得られたときであり、低価格だからといって満足度が高くなるものでない。図表−13は期待水準と価格の関係を示したもので、実際に受けたサービス水準と価格毎の期待水準の差によって満足または不満が生じていることが分かる。
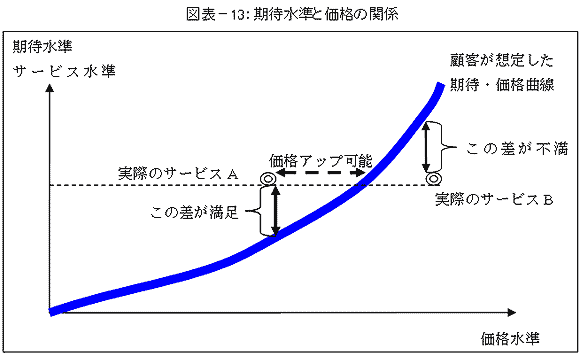
顧客の満足を得るためには、顧客が想定する価格の期待水準より高いサービスを提供すればいい訳だが、そのために原価を引上げてしまい、利益を減らす可能性もある。利益水準を維持したままで、満足度を上げる方法として
・ 顧客が他のプロバイダーと比較できない差別化された独自サービスを提供する。
・ 顧客が想定しなかった「びっくり」サービスを提供し、意外な利得感を与える(例えば、前節で述べた「ガイドブック」の抽選番号の当選者に「お土産」などの特典)。
注意しなければならないのは、全体の満足度は個々のサービス(「泊」「食」「浴」「遊」)の足し算(総和)ではないことである。一つでもマイナス評価のサービスがあれば、掛算で全体の評価もマイナスになってしまう。こうした事態を避けるために、提供する個々のサービス毎に顧客の期待水準を測定し、それを上回るサービスを提供するよう努めなければならない。そのためには、サービス毎に品質基準を設定し、原価管理も含めた管理体制を取る必要があろう。また、そうすることで担当部門のスタッフから新しいサービス提案や創意工夫も生まれてくるだろう。なお、顧客の満足度は応対する従業員・スタッフの態度や言葉遣いで大きく影響を受けるため、普段より研修やトレーニングを実施して従業員・スタッフの知識や接客態度の向上に努めることも重要である。
なお、宿泊サービスは一種の装置産業であり、空室などで施設稼働率が下がればその分収益は確保できないため、可能な限り集客努力を行なう必要がある。インターネットなどIT技術と「タイムサービス」的な割引制度を組み合わせて使うことで、残っている部屋の販売も可能になる。特に、多様な宿泊プランや食事サービスを持っている施設には有効な手段となるだろう。
3 販売・チャネルとプロモーション
(1)旅行会社
多くの温泉地や宿泊施設は、集客の大部分を旅行会社に依存している。本来は代理店で、サービス提供者が直接取りきれなかった利用者や見込み客を集める業務であるが、実態としては、集客の要として、個別のサービス提供業者だけでなく、消費者に対しても価格やマーケティング面で大きな影響力を行使している。その理由として
・ 温泉利用者の大多数が居住する都市部に所在するため、利用者との接点が多く、ニーズの把握が可能であると同時に、見込み客へのアプローチも容易である。このため、地方に偏在する温泉地に比べて強大な集客力を有している。
・ 利用者の旅行ニーズに合わせ、様々の観光資源や施設、交通手段についての情報を集めデータベース化している。この情報力を使って消費者にコンサルティングを行うほか、交通、宿泊、観光の予約・手配・決済などを一括手続きするワンストップサービスの利便性を提供して信頼性を勝ち得ている。また、顧客に対して利用施設についての満足度調査を行ない、提供するサービスの品質維持に努めている。
・ 鉄道会社など大企業から派生した旅行会社が多く、優秀な人材の募集も容易で、周遊旅行やパッケージツアーなどの企画力も高い。こうした企画旅行の集客力を背景に個別のサービス提供業者に価格面や設備面で交渉力(バーゲニングパワー)を発揮してきたし、業者の方も(顧客紹介を得るために)こうした要請を甘受してきた。
この関係を図示すると図表−14のようになる。

こうした構図は、顧客が温泉地や宿泊施設などのサービス情報について少しの情報量しか持たず、また、反対に温泉地や宿泊施設のサービス提供者は顧客ニーズについて情報量が少ないという「情報偏在」があり、この偏在した情報を旅行会社が独占的につなぐという形になっている。旅行会社には、顧客やサービス業者から広範囲に集めた情報を分析し、資源の最適配分に役立てるというブローカーとしての使命があるが、ともすると自社利益の追求のため、情報機能をフル活用して、団体職場旅行のような大量生産・大量消費型の旅行を観光地や温泉地に送り込み、ベルトコンベアに乗ったような画一的、流れ作業的なサービス提供で効率のみを追求しがちになる。この結果、多くの温泉地や宿泊施設は個性を失い、どこへ行っても同じような風景しか見いだせなくなってしまったのは前述の通りである。
(2)新しい波
「アンアン」「ノンノ」に代表される若い女性向き情報雑誌やガイドブックなどの普及により、消費者は温泉地についての情報量を格段に増すことができた。雑誌の特集に乗ってこれまで余り団体客の訪れなかった「秘湯」や「ランプの宿」へ個人もしくは小グループで出かけるようになった。だが、こうした手間がかかる割に単価が低い旅行は、旅行会社にとって収益上魅力的でないため、あまり関心が払われてこなかった。彼らは、メディアの助けを借りながらであるが、自分たちで旅行プランを立て、旅館を予約し、お仕着せでない旅を楽しみ、新鮮な感動を味わった。彼らが旅先での経験や旅で得た感動を、初めは口コミで、次いでパソコン通信のチャットで、そしてインターネットのホームページやメールで発信するようになった。こうした情報を読んで関心を持った人たちは、掲載されている温泉地や旅館に直接コンタクトを取るようになった。こうした状況変化にいち早く反応したのが、これまで旅行会社からの恩恵が少なかった温泉地や宿泊施設である。彼らはインターネットを導入し、ホームページを通じて自地域や施設の情報を発信すると共に、IT技術を使いインターネット上で予約を受け付けるようになった。(パソコンの低廉化と高速通信回線ネット網普及のおかげで、インターネットでの情報発信はパンフレットを作成・配布するより費用は少なくて済む)
このことにより、中間業者を排除した形で、消費者とサービス提供者が直接取引できる、いわばB
to Cの体制が完成したことになる。従来も電話や手紙による直接取引はあったが、それは再訪者など特定者に限られ、その対象数も少ないものであった。しかし、インターネットでは宿泊する部屋の様子から食事内容、浴室の状況まで膨大な情報を得ることができるほか、他のサービス業者との比較もでき、初めての客も安心して取引ができる点で画期的であった。また、サービス業者にとっても、旅行会社への依存度を減らすことで価格交渉力を取り戻すことができるほか、割引を臨機応変に使うことで客室稼働率を向上できるなど利点は多い。このため、インターネットを使った情報発信と取引は今後もますます増えると予想される。図表−15は、情報発信の主体とそのメディアである。
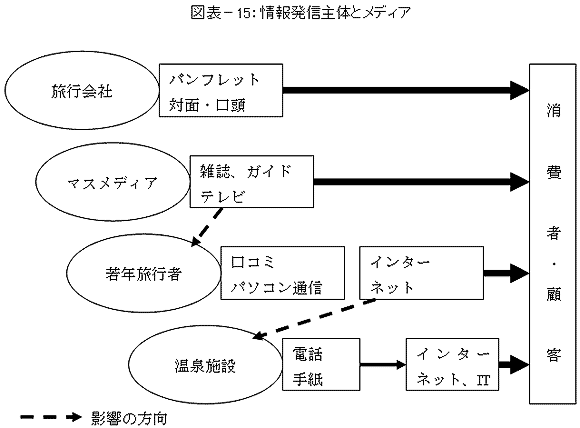
(3)コミュニケーション
前節では、温泉地や温泉施設がインターネットを使って自ら情報発信を行なうようになった経緯を見た。確かに、インターネットはコスト的にも、適時性でも、また伝える情報量においても他に比べて非常に有効な手段である。しかし、万能ではない。例えば、年齢層別にインターネットの利用状況を見ると、男性50代で利用経験があるのは37%と4割を切っており、60代以上の男性では13%と8人に1人しか使ったことがない。また、女性では更に低く、50代で25%、60代以上では6%でしかない。(図表−17)これらの年齢層は、温泉利用度や利用意欲が最も高い層であるが、彼らを対象としたメッセージをメールやインターネットで案内しても、大半の対象者には届かず、努力は水泡に帰すことになる。一般に高齢者へは新聞広告や手紙が有効と言われているが、ターゲットとする対象顧客群毎に効果の高い方法を選択すべきであろう。
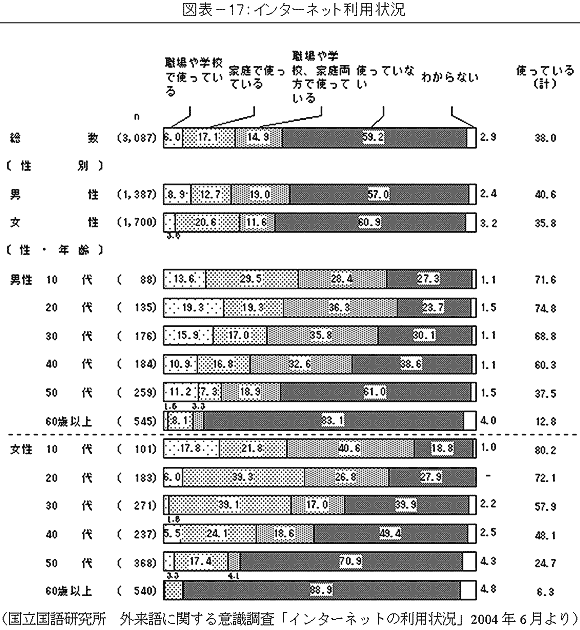
生命保険などセールスの世界では新規顧客を獲得するには、既契約の顧客から別の保険を契約するに比べて5倍の努力やコストがかかると言われているが、温泉地や宿泊施設でも同様のことがいえる。すなわち、新規客の開発より、かつて温泉地を訪れたり、宿泊した人々をターゲットに再訪、再々訪を働きかける既存客の開拓の方が容易である。彼らに来訪時の楽しい記憶を呼び覚ますことができれば(そのために満足度を高める努力をしているのであるが)、新たに案内するサービスに対しても関心を持ってくれる可能性が高い。幸い、日本の温泉地は周囲に豊富な自然があり、また、郷土色豊かな芸能や工芸があるので、四季折々の風物詩に添えてこうした案内を出すことができる。こうした活動を地道に続けることで温泉地や施設に対する高い顧客ロイヤリティを確保することが可能となろう。
|
|


